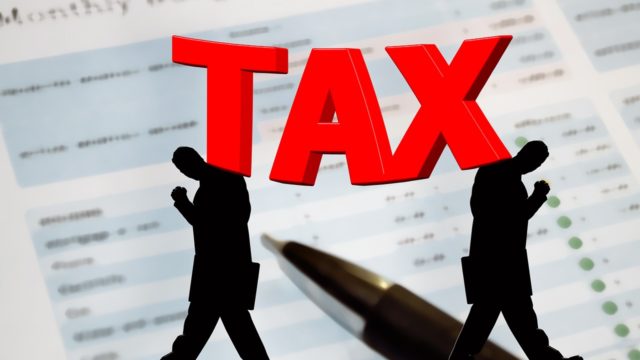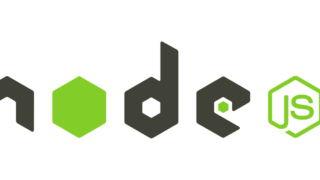管理人
最新記事 by 管理人 (全て見る)
- 【テスター】最強フリーランサーになろう!高収入と好条件を獲得する戦略 - 2022年9月17日
- 【AWS】最強フリーランサーになろう!高収入と好条件を獲得する戦略 - 2022年9月17日
- 【Unity】最強フリーランサーになろう!高収入と好条件を獲得する戦略 - 2022年9月17日
フリーランスとして働く場合、厚生年金に加入できないため、会社員として働く人よりも年金の面で不利になってしまいます。そこで今回は、老後にもらえる年金の金額を増やすための上乗せ年金制度を5つ紹介していきたいと思います。
目次
フリーランスはもらえる年金が少ない
フリーランスとして働く場合、基本的には国民年金だけへの加入になってしまいますが、その場合、老後にもらえる年金は厚生年金に加入している人に比べて大きく減ってしまいます。国民年金の支給額は満額でも64,941円(平成30年度の金額)となっており、厚生年金の平均受給額14万5,638円と比べると半分以下の金額しか支給されないことになります。
コツコツと自分で貯金ができる人であれば別ですが、毎月6万円ちょっとのお金では生活していくのが難しいと思いますので、国民年金とは別に、自分でフリーランス向けの年金に加入して老後に備える必要があります。
老後の資金対策として活用したい制度
さっそくここからは、将来もらえる年金を増やすための制度について紹介していきます。
1. 付加年金
付加年金は、国民年金の保険料に、毎月400円プラスで支払うだけで、もらえる年金額を増やすことができる制度になり、この制度を利用することによって、200円×納付月数分の金額が毎年プラスでもらえることになります。
例えば、付加年金を30年間払い続けた場合の支給額は、200円 × 12ヶ月 × 30年 = 72,000円(年額) となるため、毎月の国民年金の支給額が6000円増えることになります。
ちなみに毎月自分で収める金額は400円なので、30年間保険料を納めた場合の総負担額は、400円 × 12ヶ月 × 30年 = 148,000円となり、年金がもらえるようになってから、たったの2年で元がとれることになります。
2. 個人年金
個人年金には保険型と貯蓄型の2種類があり、個人年金保険に関しては民間の金融機関が様々な商品を提供しています。ひとつ目の付加年金とは違って、自分で民間企業が提供する複数の商品の中から種類を選んで加入することになるため、メリットとデメリットをもとに、それぞれの商品を比較した上で加入するかどうかを決める必要があります。
3. 小規模企業共済
3つ目は「小規模企業共済」という制度です。よく、フリーランスのための退職金制度のようなものと言われており、1,000円〜70,000円までの金額の範囲で毎月積立てを行い、その金額に応じてお金を共済金として受け取れるようになっています。長期スパンで継続して積立を行えば、自分が実際に払った以上の金額が受け取れて、なおかつ節税にもつなげられます。
一方で毎月の積立金を途中で減額したり、解約してしまった場合は損をしてしまう可能性もあるため、しっかりと計画性をもって運用していく必要があります。
小規模企業共済で退職金を準備する5つのメリットと3つの注意点
4. 国民年金基金
4つ目に紹介するのは「国民年金基金」という制度です。こちらは公的な年金制度になり、厚生年金と国民年金とで生じる差分を、国民年金基金に加入する事によって埋めることができます。他の制度とはちがって、もらえる年金額は自分の掛金額に応じて確定するため、他の制度よりも将来の見通しが立てやすいのが特徴です。また支払った金額は、全額控除の対象になるため高い節税効果も期待できます。
ちなみに途中で掛金額を増やすことが可能ですが、一度加入すると、途中で自己都合でやめることができなかったり、国民年金基金と1つ目に紹介した付加年金は併用できないといった特徴があるため注意が必要です。
国民年金基金の詳細については、こちらの漫画に分かりやすくまとまっていますので参考にしてみてください。
5. 個人型確定拠出年金「ideco(イデコ)」とは
最後に、個人型確定拠出年金の「ideco(イデコ)」という制度について紹介します。イデコは定期預金・保険・積立投資などの金融商品を自分で選び、毎月決まった金額を積立てて投資していって60才以降のタイミングでお金を受け取る制度になります。先ほどの国民年金基金と同じく、支払った全額が所得控除の対象になるため、高い節税効果も期待できます。
一方で、先ほどの国民年金基金と違うのは自分の投資方法によって、もらえる金額が変化するところです。最終的な受け取り金額が、積立てた金額を上回ることもあれば、下がってしまう可能性もあり、なおかつ、もらえる期間も決まっています。よって確実性や安定性を重視したい場合は、老後ずっと同じ金額がもらえる国民年金基金に加入する方が向いているといえます。
収入を増やしたいならエージェントの活用が一番!
エージェントを活用することで、高単価の案件をたくさん紹介してもらえます。また、案件数も多いので、数ある案件の中から自分がやりたい案件に絞れる点が魅力的です。今後どのようなスキルを伸ばしていけば、さらに獲得できる案件の単価や数を増やせるのかといったカウンセリングをしているエージェントもあります。
フリーランスとして活躍したいのであれば、複数のエージェントに登録をして、手厚いサポートを受けましょう。また、複数のエージェントに登録することで、自分の単価の平均値が割り出せたり、より多くの案件に触れることで自分の得意不得意、やりたい事が明確化されます。
まとめ
老後にもらえる年金を上乗せするための制度を全部で5つ紹介しましたが、確実性や安定性を重視したい場合には、高い節税効果も期待できる「国民年金基金」がオススメといえます。仕事を続けていく上での不安にしっかりと対処できれば、より仕事へ集中できるようになるはずです。
管理人
最新記事 by 管理人 (全て見る)
- 【超重要】「開業届け」と「青色申告書」の提出について - 2021年4月30日
- 営業コンサルからエンジニアに。月収30万から70万までの道のりを聞いてみた。 - 2019年5月6日
- PM・デザイナー・エンジニア、職種別で必要なスキルセット一覧!フリーランスエンジニアで働くために - 2018年11月24日
高収入・好条件のフリーランス案件を獲得するには
『ITフリーランス学校』は、最強フリーランサーを輩出する教育校になるために、高収入・好条件を獲得するための情報を届けるサイトです。
不況の時代を生き抜く戦略やテクニックを提供する、PG/SE/PM達のための学校です。
最強フリーランサーになるために、以下のようなことを勉強出来ます。
- フリーランスになるまでをどう過ごすのか
- フリーランスになるための手続きについて
- 単価を上げるため戦略
- 年収を2000万円を目指すためには
記事を通して全て学ぶことが可能です。
すぐにでもフリーランスになりたいと思っている方は、こちらからご登録ください。
無料のカウンセリングから案件の提供まで丁寧に対応してくれます。
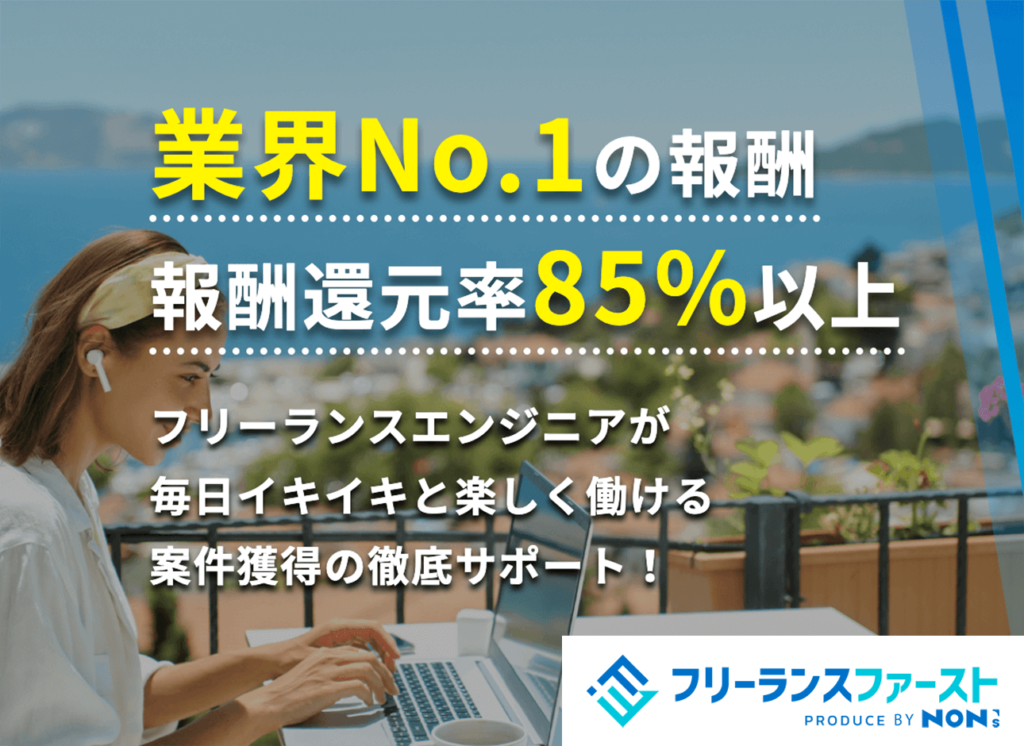 最強エージェント: 「フリーランスファースト」
最強エージェント: 「フリーランスファースト」
https://freelance-first.com/
いつの時代でも生き抜ける最強フリーランサーを目指して学んでいきましょう!